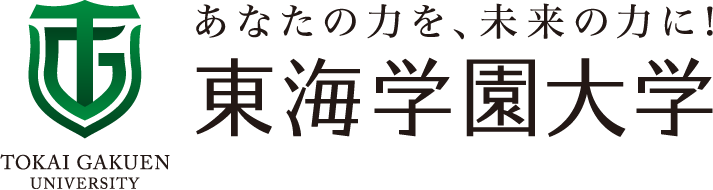山本 伸
基本情報
| 所属 | 経営学部経営学科 |
|---|---|
| 職名 | 教授 |
| 学歴 (大学卒以降) |
立命館大学文学部文学科英米文学専修 静岡大学大学院教育学研究科英語教育学専攻英米文学専修 コロンビア大学留学(国際ロータリー財団大学院奨学生) |
| 学位 | 教育学修士(英語教育学) |
| 職歴 (研究歴) |
【専任】 暁学園短期大学専任講師 暁学園短期大学助教授 四日市大学短期大学部助教授 四日市大学助教授 四日市大学教授 東海学園大学教授 【非常勤】 中日本自動車短期大学 松阪大学 三重中京大学 名古屋外国語大学 椙山女学園大学 立命館大学 中京大学 沖縄国際大学 三重大学 |
| 主な授業科目 | 外国の文学 サバイバル・イングリッシュ 海外研修準備講座 海外研修A スチューデントスキル 基礎演習 総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 卒業研究 |
| 所属学会 | 多民族研究学会(MESA/理事) ポップカルチャー学会(APOCS/副代表) 黒人研究学会(JBSA/元副代表) 日本アメリカ文学会(中部支部) 沖縄外国文学会 南島文化研究所(特別研究員) Collegium for African American Research (CAAR) |
| 専門分野 | 英語圏カリブ文学/沖縄文化研究/比較文化論 |
| 研究テーマ | 近代合理主義のオルタナティブとしての土着文化の発掘とその現代的意義付け |
| ホームページ | 山本伸のカリぶログ |
研究実績・活動
社会連携活動
CTY-FM(三重県四日市市)のラジオ番組の企画・編集・放送(パーソナリティ)
「山本伸のMonday Nite GrooVe」(毎週月曜夜7時~生放送)
学生番組「ゆるゆるたいむ♪」「コーヒータイム♪」「バズってタイム♪」「午後のキャンパス(Go Go Can!)」の企画・編集・放送(プロデューサー/ディレクター)
教育研究業績(著書)
『20世紀の日本人』(翻訳、五月書房、 1999)
『地球村の行方―グローバリゼーションから人間的発展への道』(共著、新評論、1999)
『世界の黒人文学』(共編著、鷹書房弓プレス、2000)
『クリック?クラック!』(翻訳、五月書房、2001)
『オリエンタリズムを超えて』(共訳、新評論、2001)
『地球村の思想』(共著、新評論、2001)
『中心の発見』(共訳、草思社、2003)
『浄土真宗と平和』(共著、文理閣、2003)
『資本主義と奴隷制』(監訳、明石書店、2004)
『カリブ文学研究入門』(単著、世界思想社、2004)
『黒人研究の世界』(共著、青磁書房、2004)
『カリブの風』(共著、鷹書房弓プレス、2004)
『下からのグローバリゼーション―もう一つの「地球村」は可能だ』(共著、新評論、2006)
『20世紀アメリカ文学を学ぶ人のために』(共著、世界思想社、2006)
『黒いアテナ―捏造されたギリシャ文明』(共訳、新評論、2007)
『浄土真宗と共生』(共著、文理閣、2007)
『木と水と空と』(共著、金星堂、2007)
『英語文学とフォークロア―歌、祭り、語り』(共著、南雲堂フェニックス、2008)
『水声通信―ポスト・ソウルの黒人文化』(共著、水声社、2009)
『グローバル世紀への挑戦―文明再生の智慧』(共著、 新評論、2010)
『バードイメージ―鳥のアメリカ文学』(共編著、金星堂、2010)
『南アフリカの指導者、宗教と政治を語る―自由の精神、希望をひらく』(共訳、本の泉社、2012)
『いま、世界で読まれている105冊 2013』(共著、テン・ブックス、2013)
『琉神マブヤーでーじ読本:ヒーローソフィカル沖縄文化論』(単著、三月社、2015)
『土着と近代:グローカルの大洋を行く英語圏文学』(共著、音羽書房鶴見書店、2015)
『衣装が語るアメリカ文学』(共編著、金星堂、2017)
『エスニシティと物語りー複眼的文学論』(共著、金星堂、2019)
『ブラック・ライブズ・スタディーズ』(共編著、三月社、2020)
『アメリカ映画とエスニシティ』(共著、金星堂、2024)
『ラテンアメリカ文学を旅する58章』(共著、明石書店、近刊)
『痛みの木』(五月書房新社、近刊)
教育研究業績(論文)
リチャード・ライト試論-精神的移動[指向]性を中心に-(『中部地区英語教育学会紀要17号』、pp.124-129、1988年3月)
"Folk Romance and Folk Realism in Harlem Renaissance"(『中部地区英語教育学会紀要18号』、pp.74-79、1989年3月)
"Folkloric Elements in Slave Narratives"(『中部地区英語教育学会紀要19号』、pp.215-220、1990年3月)
In the Castle of My Skin試論―主人公の精神的成長に果たすコミュニティーの役割を中心に-(『暁学園短期大学紀要23・24号』、pp.19-29、1991年12月)
カリブ文学におけるコミュニティーと自我(1)―ラブレイスとナイポールの同名短編「臆病者」の内容比較を通して-(『暁学園短期大学紀要23・24号』、pp.40-53、1991年12月)
カリブ文学におけるコミュニティーと自我(2)―トリニダードにおけるインド系コミュニティーの場合―(『暁学園短期大学紀要25・26号』、pp.14-20、1993年3月)
カリブ文学におけるコミュニティーと自我(3)―中国系作家ウィリー・チェンの視点― (『暁学園短期大学紀要27号』、pp.38-46、1994年3月)
アール・ラブレイス著『ジョージと自転車の空気入れ』(翻訳および解説)(『四日市大学短期大学部紀要28号』、pp.146-156、1995年3月)
なぜ、ドラゴンは踊れないのか―カリブ黒人作家アール・ラブレイスの視点(『黒人研究 No.65』、pp.16-21、黒人研究の会、1995年12月 )
From Williams to Lovelace― In Search of a "Place" of Their Own(Trinidad Guardian, p.7, Sep.29th, 1996)
'90 年代カリブ文学の諸相(『黒人研究 No.66』、pp.13-18、黒人研究の会、1996年12月)
ハイチ―融合する時間と空間―Edwidge DanticatのBreath, Eyes, Memory (1994)に見るもうひとつのクレオリズム(『黒人研究 No.67』、pp.26-31、黒人研究の会、1997年12月)
"Nou led, Nou la" - Haitian-American Woman Writer: Edwidge Danticat (『京都アメリカ研究夏季セミナー発表論集』、pp.169-174、立命館大学アメリカ研究センター、1998年6月)
ウィリアムズからラブレイスへ―カリブ小説における「カーニバル」の意味を中心に(『黒人研究 No.68』、pp.1-5、黒人研究の会、1998年12月) 抑圧された黒い祈り―カリブ文学に描かれた「叫びの宗教(Shouter Baptists) 」(『四日市大学短期大学部紀要 第32号』、pp.255-262、1999年4月)
内なる解放―アール・ラブレイスの小説における「成長」とは何か(『四日市大学短期大学部紀要 第33号』、pp.125-132、2000年4月)
『黒人家庭における心理療法』(1989)抜粋翻訳および解説(『四日市大学短期大学部紀要 第34号』、pp.23-40、2001年3月)
カリブ文学に見るグローカリズムの形―オリーブ・シニアの作品を例に(『四日市大学環境情報論集』第6巻第1号、pp.129-135、2002年9月)
V・S・ナイポール:その「光」と「陰」―2001年度ノーベル文学賞受賞にあたって(『黒人研究No.71』、pp.25-27、黒人研究の会、2002年12月)
“Racial Stance of Chinese in Willi Chen’s King of the Carnival”(『四日市大学環境情報論集』第7巻第1号、pp.105-110、2003年9月)
掘り起こされる「中間航路」―ブラック・ブリティッシュ作家の活躍(『黒人研究No.74』、pp.26-28、黒人研究の会 2005年3月)
“Swaying in the Heat of the Island―From Ambivalence to Dynamism in Caribbean Literature―”(『四日市大学環境情報論集』第9巻2号、pp.85-90、2006年3月)
「なぜ、沖縄の吉野家にはカウンター席がないのか?―沖縄型コミュニケーションの真髄とグローカリズム」(『APOCS』、pp.61-72、日本ポップカルチャー学会、2007年3月)
“RE-COMMUNICATING WITH THE DEAD—A Japanese Perspective on Edwidge Danticat’s Krik? Krak!”(『四日市大学環境情報論集』第11巻1号、pp.21-26、2007年9月)
“Swaying in time and space: the Chinese Diaspora in the Caribbean and its literary perspectives”(Asian Ethnicity, Volume 9, Issue 3, pp.171-178, Routledge, October 2008)
「黒人研究と平和/ボーダーを越境するダイアローグ:Swaying in the Heat of the Islands―カリブ文学と『平和』」(黒人研究の会編『黒人研究 No.78』、pp.9-10、2009年3月)
ポスト・ソウルとスパイク・リー―『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』(1986)にみる「新たな黒人の美学」(黒人研究の会編『黒人研究 No.79』、pp.28-30、2010年3月)
書評 エドウィージ・ダンティカ著『愛するべきものへ、別れのとき』(『多民族研究 第4号 2011』、pp.142-4、多民族研究学会 2011年3月))
Continental Crossings, Continental Divides: American Studies in Japan and England (co-author: Christopher Mulvey)(『四日市大学環境情報論集』第17巻第1号、pp.137-147、2013年9月)
エドウィージ・ダンティカ再考―民俗文化再生のための多層的コミュニケーション(『東海学園大学 人文科学研究編』 No.26)
教育研究業績(その他)
【大学用教科書】
『特選カリブ短編集-アール・ラブレイス-』(青磁書房)
『ふたつの大陸、ひとつのアメリカ』(弓プレス )
"Reading Better, Thinking Better" (青磁書房)
『英語で学ぶスポーツ科学』(南雲堂)