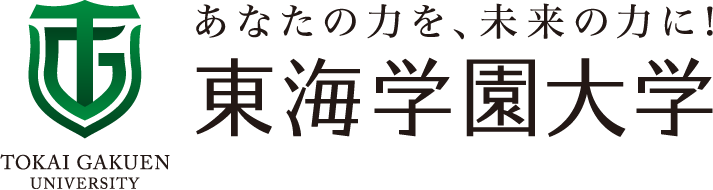池田 佳代
基本情報
| 所属 | 経営学部経営学科 |
|---|---|
| 職名 | 教授・学長補佐(キャリア支援) |
| 学歴 (大学卒以降) |
国立千葉大学工学部画像工学科卒業 工学士 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科修了 技術経営修士(専門職) 国立大学法人電気通信大学大学院電気通信学研究科人間コミュニケーション学専攻博士後期課程修了 博士(学術) |
| 学位 | 博士(学術)国立大学法人電気通信大学大学院 |
| 職歴 (研究歴) |
大日本スクリーン製造(株) (有)エクセリードテクノロジー 代表取締役 武蔵野大学 非常勤講師 清泉女学院大学人間学部 准教授 環太平洋大学 経営学部 現代経営学科 准教授 環太平洋大学 現代経営研究所 副所長 環太平洋大学 経営学部 現代経営学科 学科長 環太平洋大学 経営学部 現代経営学科 教授 東海学園大学 経営学部 准教授 同大学院経営学研究科担当(現在に至る) 東海学園大学 経営学部 教授(現在に至る) |
| 主な授業科目 | 経営情報論、情報ネットワーク演習、経営情報システム論、ビジネスデータ分析、専門演習C「プロジェクトマネジメント」、スチューデントスキル、基礎演習、総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、卒業研究、経営情報特論(大学院)、ケーススタディⅡ(経営情報)(大学院)、演習Ⅰ・Ⅱ(大学院) |
| 所属学会 | 情報処理学会、映像情報メディア学会、社会情報学会、情報通信学会、社会調査協会、日本行動計量学会、イノベーションファクター研究会 |
| 専門分野 | 経営情報論、データサイエンス、社会システム工学 |
| 研究テーマ | メディアによる情報信頼と情報行動に関する研究 地域医療機関選択に関わる患者の情報信頼と情報行動についての研究 デジタルトランスフォーメーション(DX)と組織コミュニケーションに関する研究 |
| ホームページ | researchmap 研究者情報 |
研究実績・活動
社会連携活動
岡山市「学生イノベーションチャレンジ推進プロジェクト」正副リーダー向けの「大学生向けコンプライアンス教室」の実施(2019年9月)
公益財団法人岡山県産業振興財団 『スター☆ベンチャー誕生』審査員(2019年10月~2019年11月, 2020年9月~10月)
丸善雄松堂株式会社との連携推進(知の創造プロジェクト・ビジネスプランコンテスト企画運営)
「イノベーション・ファクター研究会」(東京理科大学MOT(技術経営)修了生メンバー会)設立、会員(2010年~現在に至る)
「笑顔あふれる矢津の里プロジェクト」と共同地域活性化事業促進(2017年4月~2019年3月)
岡山市産業観光局産業振興・雇用推進課と課題体験事業「岡山市大学生店舗応援事業」を共同開催
瀬戸税務署、岡山東税務署との連携推進(毎年度、租税教室を開催)(2016年4月~2020年3月)
岡山県産業労働部産業振興課との連携推進(毎年度「ベンチャーミーティング」パネルディスカッションを主催)(2016年4月~2020年3月)
岡山市女性活躍シンポジウム・パネルディスカッション・コーディネーター(2020年11月)
おかやま創生高校パワーアップ事業 地域共育審議会委員(2016年6月~2019年3月)
長野市男女共同参画審議会委員(2014年4月~2016年3月)
西東京市地域情報化計画策定審議会委員(2012年10月~2014年3月)
内閣官房IT室、経済産業省 文字情報基盤推進委員会事務局(2012年4月~2013年3月)
東北大学電気通信研究所 共同研究委員(2008年4月~2009年3月)
独立行政法人 情報処理推進機構 社会基盤センター(旧 技術本部 国際標準推進センター )専門委員(2012年4月~2022年3月)
独立行政法人 情報処理推進機構オープンソフトウェア・センター企画グループ 研究員(2007年4月~2012年3月)
国立情報学研究所 プロジェクト研究員(2006年4月~2007年3月)
東京大学国際・産学共同研究センター 科学技術振興特任研究員(2006年4月~2007年3月)
ディジタル&次世代コンテンツ調査研究会WG委員(情報通信ネットワーク産業協会)(2003年4月~2009年3月)
次世代ドキュメント研究会(経済産業省/情報処理事業振興協会)事務局(2003年4月~2004年3月)
教育研究業績(著書)
『緊急事態のための情報システム』(共訳)(翻訳)近代科学社, pp.287-308, 2014年8月
『「知」の世界をひろげよう』(共著)(教科書)武蔵野大学, pp.59-62, 2013年4月
教育研究業績(論文)
「How brand loyalty and its marketing activities affect Japanese fashion companies' financial performance」(共著)『Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal』 DOI 10.1108, 2024年10月
「A qualitative comparative study of Japanese fashion brands via profiling young shoppers」(共著)『International Journal of Retail & Distribution Management 51(2)』pp.170-189, 2022年10月
「Brand equity effects on financial performance in Japanese fashion market: applying complexity theory via fsQCA」(共著)『Journal of Global Fashion Marketing』pp.30-43, 2021年9月
「メディアに対する信頼意識と情報行動との関係性に関する考察」(共著)『情報社会学会誌 15(1)』pp.23-35, 2020年12月
「SNSによる情報信頼と情報行動についての基礎的研究」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (16) 』pp.81-88, 2020年3月
「SNSにおける情報拡散意識の探求」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (16) 』pp.97-106,2020年3月
「教育効果としてのワーク・エンゲイジメントの観察」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (14) 』pp.137-146, 2019年3月
「サービス・マネジメントから見た教育に関する一考察」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (14)』pp.83-92, 2019年3月
「雄町米プロジェクト報告 -留学生による酒造り体験の実践 -」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (13)』pp.119-123, 2018年3月
「外国人労働者の環境に関する一考察 ― ベトナム人看護師・介護福祉士候補者を対象として ―」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (12)』pp.19-28, 2018年3月
「EPAに基づくベトナム人看護師・介護福祉士における ワーク・エンゲイジメントの考察」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (12)』pp.147-156, 2018年3月
「ネット依存を防ぐための情報教育に関する一考察―長野県の高校と大学を対象にした質問紙調査を通して―」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (11)』pp.219‐227, 2017年3月
「コミュニティ化戦略を展開する地域企業における信頼形成の影響度考察」(共著)『環太平洋大学研究紀要 (11)』pp.243‐252, 2017年3月
「プロジェクションマッピングが与える社会的インパクトの考察」(共著)『清泉女学院大学人間学部研究紀要 (13)』pp.37-48, 2016年3月
「IT利用と地域活動に関する一考察」(共著)『The Basis : 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 (5)』pp.231-244, 2015年3月
「日本語オープンフォントの派生に関する考察」(共著)『清泉女学院大学人間学部研究紀要 (12)』pp.3-14, 2015年3月
「質問紙調査と行動観察実験における信頼性確保のための一考察 : 情報セキュリティ対策に おける調査と実験を対象に」(共著)『清泉女学院大学人間学部研究紀要 (11)』pp.37-48, 2014年3月
「ソーシャルメディアを活用した社会設計の考察」(共著)『The Basis : 武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要 (4)』pp.197-210, 2014年3月
「言語学習初心者に優しい多言語入力支援システムの開発とその評価」(共著)『情報処理学会情報アクセスシンポジウム2010 article 3』pp.1-8, 2010年9月
「振り込め詐欺と地域社会との関連性研究」(共著)『情報社会学会誌 5(1)』pp.5-17, 2010年6月
「情報通信基盤としての文字処理環境の整備に関する研究」(単著)電気通信大学 博士論文, pp.1-239, 2010年3月
「情報通信基盤としての日本語パブリックフォントライセンスの研究:DREの視点から」(共著)『情報通信学会誌 27(2)』pp.37-54, 2009年9月
「情報通信基盤としての高品質日本語オープンフォントに関する検討」(共著)『情報社会学会学会誌 4(1)』pp.105-119, 2009年6月
「Proposal for a multilanguage text input support system that is easy for beginner language learners.」(共著)『Proceedings of the 3rd International Universal Communication Symposium, IUCS 2009, Tokyo, Japan, 3-4 December 2009』pp.109-114, 2009年
「Experimental Investigation of Differences among Web Search Engine」(共著)『The First Workshop on Information Credibility on the Web 』pp.109-114, 2007年6月
「A New Distributed Behavioral Model for Non Time-based CG System」(共著)『International Workshop on Advanced Image Technology』pp.73-74, 2006年1月
「KANSEI PERSPECTIVE: IMAGE CHARACTERISTICS EXPRESSION BY MANUAL DESCRIPTION FOR IMAGE RETRIEVAL」(共著)『International Workshop on Advanced Image Technology 』pp.291-296, 2006年1月
教育研究業績(その他)
「地域医療機関情報に関する研究~医療機関選択における情報の重要度と広告規制認知を中心に~」(共著) 『2023年社会情報学会大会論文集』pp.133-138, 2023年9月
「デジタルトランスフォーメーション(DX)と組織コミュニケーションに関する一考察 」(共著)『東海学園大学研究紀要 社会科学研究編26』 pp.19-31, 2021年3月
「映画館利用に関する質問紙調査の考察 ~世代間比較を中心に~」(単著)社会情報学会(SSI) 学会大会, 2015年9月
「映画館のある風景~長野市での質問紙調査による考察~」(単著)社会情報学会(SSI) 学会大会, 2014年9月
「農山村地域に知識と情報の対流を促す“農村ストーリー生成システム”の提案」(共著)農業農村工学会大会講演会講演要旨集,2013年8月
「ソーシャルメディアが及ぼす社会的インパクトの考察」(共著)情報処理学会シンポジウムシリーズ(CD-ROM), 2013年7月
「農村地域に知識と情報の対流を促すSNSの導入上の課題」(共著)農業農村工学会大会講演会講演要旨集, 2012年9月
「農村地域に知識と情報の対流を促す多階層連携システムの概要とその導入・運用手法」(共著)情報処理学会研究報告(CD-ROM), 2012年4月
「農村地域に知識と情報の対流を促す多階層連携システムの概要とその導入・運用手法」(共著)情報処理学会 第119回情報システムと社会環境研究発表会2012-IS-119, 2012年3月
「言語学習初心者に優しい多言語入力支援システムの開発とその評価」(共著)情報処理学会 情報アクセスシンポジウム(IAS)2010, 2010年9月
「振り込め詐欺と地域社会との関連性研究」(共著)情報社会学会 2010年度年次研究発表大会, 2010年6月
「サイバー犯罪と実社会との関連性研究」(共著)情報処理学会 情報セキュリティ心理学とトラスト研究発表会, 2009年10月
「高品質日本語オープンフォント活動の試みと社会的意義」(共著)情報社会学会 2009年度年次研究発表大会, 2009年6月
「主要検索エンジンサイトランキング調査とメタサーチエンジンの研究開発」(共著)信頼の情報通信メカニズムワークショップ, 2007年3月
「デジタル文章流通における伏せ字付文章の認知特性」(共著)電子情報通信学会「ヒューマン情報処理研究会」「パターン認識・メディア理解研究会」合同研究会, 2007年2月
「テキスト半開示方法の提案」(共著)画像電子学会年次大会予稿集, 2006年6月
「テキストインデキシング方法の性能評価」(共著)画像電子学会年次大会予稿集, 2006年6月
「テキストインデキシング方法の提案」(共著)画像電子学会年次大会予稿集, 2006年6月2
「画像検索のための3Dインターフェースの検討と課題」(共著)情報処理学会研究報告, 2006年3月
「BOIDアルゴリズムにおけるクラスタ度評価」(共著)情報処理学会研究報告, 2006年1月
「画像中の被写体に対する感性を用いた特徴解釈の検討」(共著)電子情報通信学会大会講演論文集, 2005年9月
「デジタルメディアイノベーションと社会への影響」(共著)社会情報学フェア2005(日本社会情報学会第10回研究大会), 2005年9月
「ITによるコミュニケーション手法の変化と知識創造への影響」(共著)経営情報学会 2005年春季全国研究発表大会D1-2, 2005年6月
「画像検索をサポートするカメラアングルを用いたコンテンツ分類」(共著)情報処理学会研究報告, 2005年3月
「画像検索のための3Dインターフェースとシステム適応検討」(共著)情報処理学会研究報告, 2005年3月
「カメラアングルと被写体の位置情報を用いた画像分類の検討」(共著)情報処理学会全国大会講演論文集, 2005年3月
「曖昧な記憶画像からクエリーを生成するための検索インターフェースの検討」(共著)画像電子学会年次大会予稿集, 2005年
「デジタルコミュニケーション技術のイノベーション事例の考察」(共著)経営情報学会 全国研究発表大会要旨集, 2005年
「被写体の位置情報を用いたコンテンツ分類」(共著)映像情報メディア学会技術報告, 2004年12月
「被写体の位置情報を用いたコンテンツ分類」(共著)情報処理学会研究報告[オーディオビジュアル複合情報処理], 2004年12月
「被写体の位置情報を用いたコンテンツ分類」(共著)電子情報通信学会技術研究報告. CS, 通信方式, 2004年12月
「画像検索のための3Dインターフェースの有効性検証実験」(共著)画像電子学会研究会講演予稿, 2004年10月
「立体映像におけるクロマキー合成の効果に関する研究」(共著)画像電子学会研究会講演予稿, 2004年10月
「立体視における適切なテキスト表現と表現手法の拡張に関する研究」画像電子学会研究会講演予稿, 2004年10月
「奥行き情報を用いた画像検索インターフェースの検討」画像電子学会研究会講演予稿, 2004年10月
「立体視における適切なテキスト表現と表現手法の拡張に関する研究」情報科学技術フォーラム, 2004年8月
「立体映像におけるクロマキー合成の効果に関する研究」情報科学技術フォーラム, 2004年8月
「高度画像検索のための直感的インターフェース」(共著)情報科学技術フォーラム, 2004年8月
「立体視における適切なテキスト表現と表現手法の拡張に関する研究」(共著)情報科学技術フォーラム一般講演論文集, 2004年8月
「高度画像検索のための直感的インターフェース」(共著)情報科学技術フォーラム一般講演論文集, 2004年8月
「映像検索のためのクエリー生成とインターフェース構築」(共著)情報科学技術フォーラム一般講演論文集, 2004年8月
「コンテンツ制作のための高度映像検索の検討」(共著)映像情報メディア学会年次大会講演予稿集, 2004年8月
「画像検索のための3Dインターフェースの有効性の検証」(共著)情報処理学会研究報告, 2004年6月
「高度映像検索のためのメタデータ記述とシステム開発」(共著)情報処理学会研究報告, 2004年6月
「IPMP実装による次世代型コンテンツ流通システムの構築」(共著)情報処理学会研究報告, 2004年3月
「画像検索のための3Dインターフェース」(共著)情報処理学会研究報告, 2004年3月
特記事項
【競争的資金】
「地方創生に向けた市民参画型コミュニティ形成に関する研究」(研究分担者)日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) , 2022年4月 - 2026年3月
「無意識な習慣行動による小売業におけるロイヤルティの創出に関する研究」(研究分担者)日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) , 2021年4月 - 2025年3月
「災害コミュニケーションにおける信頼度判定研究」(研究分担者)日本学術振興会: 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 2016年4月 - 2019年3月
「雄町米プロジェクト」(研究分担者)福武教育文化振興財団: 文化活動助成,2017年4月 - 2018年3月
「農村地域における知の伝達と創出を支える次世代ICT基盤技術の研究開発」(研究分担者)総務省SCOPE: ICTイノベーション創出型研究開発(ユニバーサル・コミュニケーション技術) に係る研究開発,2010年4月 - 2013年3月
「簡単映像コンテンツ制作のための高度映像検索技術に関する研究(研究開発)」(研究分担者)総務省: 特定領域重点型研究開発(次世代ヒューマンインターフェース・コンテンツ技術)SCOPE、2003年4月 - 2006年3月
【受賞】
2009年6月 プレゼンテーション賞, 情報社会学会
2008年3月 優秀研究員表彰, (独)情報処理推進機構(IPA)
【資格】
専門社会調査士
情報処理技術者試験「ITパスポート」経済産業省国家資格
エマージェンシーファーストレスポンス CPR/AED/First Aid インストラクター認定
情報処理技術者試験「応用情報技術者試験」経済産業省国家資格
LEGO®SERIOUS PLAY®メソッドと教材活用トレーニング修了認定ファシリテーター