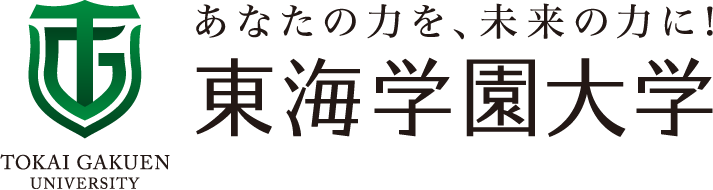中村 泰輔
基本情報
| 所属 | 教育学部教育学科 |
|---|---|
| 職名 | 准教授 |
| 学歴 (大学卒以降) |
東京大学理学部地球惑星物理学科卒業 筑波大学大学院教育研究科修士課程(教科教育専攻理科教育コース)修了 |
| 学位 | 学士(理学) 修士(教育学) |
| 職歴 (研究歴) |
看護専門学校 非常勤講師(看護物理学) 私立中学校・高等学校 非常勤講師・常勤講師(理科) 私立中学校・高等学校 教諭(理科) 東邦大学 理学部 非常勤講師(理科指導法Ⅰ、教育方法論(教育方法とICT活用)、教職実践演習、教育実習Ⅰ) 鹿児島大学 教育学部 非常勤講師(中等理科教材論、理科教育特講) 静岡大学 グローバル共創科学部 非常勤講師(入学前教育:数学) 静岡大学 教育学部 非常勤講師(中等理科教育法Ⅲ) 静岡大学 理学部 非常勤講師((中等)理科教育法Ⅲ) |
| 主な授業科目 | 理科研究、理科指導法、理科指導法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、物理学概論Ⅰ・Ⅱ、物理学実験Ⅰ・Ⅱ、基礎演習Ⅲ・Ⅳ、専門演習Ⅰ・Ⅱ、教育キャリア演習Ⅰ |
| 所属学会 | 日本理科教育学会、日本科学教育学会、日本物理教育学会、日本教材学会、日本教科教育学会、日本エネルギー環境教育学会 |
| 専門分野 | 理科教育、物理教育 |
| 研究テーマ | Nature of Scientific Inquiry(NOSI)(科学的探究の本質、科学的探究の本性)について 理科教育・STEM/STEAM教育・科学系部活動等とNOSIとの関連について IBDPの物理指導について |
研究実績・活動
社会連携活動
全国高等学校アマチュア無線連盟(全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部設立準備会)事務局長(2014~2024)・事務局員(2024~)
ARDF(Amateur Radio Direction Finding)審判員講習会講師(2022)
国際アマチュア無線連合(IARU)第Ⅲ地域ARDF選手権大会日本代表チームオフィシャル(2015)
スーパーサイエンスハイスクール情報交換会 教諭等分科会 司会(課題研究について)(2014)
全国高等学校総合文化祭(いばらき総文2014)アマチュア無線部門裁定長(2014)
スーパーサイエンスハイスクール情報交換会 教諭等分科会 発表(中高一貫教育および地域の特性を生かした国際性の育成)(2013)
教育研究業績(著書)
磯﨑哲夫編著(2023)『日本型STEM教育のための理論と実践』学校図書 「Nature of Scientific Inquiry を導入したSTEM教育の指導法の検討」pp.82~91を大嶌竜午と共同で執筆
山本容子・松浦拓也編(2021)『新・教職課程演習 第20巻 中等理科教育』協同出版 「中学校理科の『エネルギー』領域の内容構成と特徴」pp.32~34、「大学との接続・連携を意識した高等学校理科の指導法」pp.118~121、「観察・実験器具の整備・自作」pp.230~233ぼの計3項目を単独執筆
大髙泉編(2017)『理科教育基礎論研究』協同出版 「ストーリー性指向理科教育アプローチの特質と実践上の課題」pp.196~210を単独執筆
大髙泉編著(2013)『MINERVA21世紀教科教育講座 新しい学びを拓く理科 授業の理論と実践 中学・高等学校編』ミネルヴァ書房 「高等学校物理の内容構成」pp.81~84を単独執筆
下田好行編集代表(2009)『「知の活用力」をつける理数教育 中学校理科の教材開発・授業プラン 物理・化学』学事出版 「見えないものを見るためには? ~人間生活における「見る道具」としての放射線~」pp.134~141を単独執筆
日本理科教育学会編(2002)『これからの理科授業実践への提案(理科ハンドブック1)』 大髙泉・中村泰輔「総合的な学習と理科学習との関連性」pp.112~115のうち、4(3)フィールドワークの充実を執筆
教育研究業績(論文)
中村泰輔(2025)「科学的探究の本質(NOSI)の理解促進と科学系部活動との関連についての基礎的考察 ―アマチュア無線を主とする部活動の教育的意義に着目して―」『東海学園大学研究紀要』第30号 人文科学研究編 pp.65~77
中村泰輔・小笹哲夫(2022)「国際バカロレア(IB)日本語デュアルランゲージ・ディプロマプログラムにおける理科科目の実践」『理科教育学研究』(日本理科教育学会学会誌)第63巻 第1号 pp.3~13
中村泰輔(2021)「理科教育におけるNOSI(Nature of Scientific Inquiry)の理解を促す指導法の特質 ―“Argument-Driven Inquiry in Physical Science: Lab Investigations for Grades 6–8”を事例として―」『理科教育学研究』(日本理科教育学会学会誌)第62巻第1号 pp.297~307
中村泰輔(2020)「大学・研究機関との全校的・継続的連携で,生徒の探究を支える―筑波研究学園都市に位置するSSHとしての取り組み―」『理科の教育』(一般社団法人日本理科教育学会編、東洋館出版社) 2020年5月号 pp.17~19
福田成穂・中村泰輔(2016)「高校生が有する Nature of Scientific Inquiry の理解の実態 ―VASI アンケートを用いた調査から―」『日本科学教育学会研究会研究報告』Vol.30 No.6 pp.55~60
中村泰輔(2008)「NEED教材の翻訳・出版への取り組み ―教材開発ワーキンググループ NEED勉強会の活動―」エネルギー環境教育実施上の特色と問題点の解決への具体的方策の解明―エネルギー教育の地域拠点大学と実践校とのネットワークを基にして―(筑波大学エネルギー教育研究会報告書)pp.41~44
中村泰輔(2006)「中学校における放射線野外測定と地域資源の活用について」『ドイツ・アメリカ等の学校教育における環境学習・カリキュラムのシステム化の研究―地域との連携による環境学習資源の有効活用をはかって―』(研究代表者:大髙泉(筑波大学大学院人間総合科学研究科教授)2003~2005年度文部省科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書)pp.143~148
中村泰輔(2004)「アイデアの発生場面を重視した光波の授業 : 物語性を基に」『物理教育』(日本物理教育学会学会誌)第52巻第3号 pp.223~227
中村泰輔(2003)「事例調査を通じたスーパーサイエンスハイスクールの現状と課題」国立教育政策研究所 知識社会におけるリーダー養成に関する国際比較研究(政策研究機能高度化推進経費 研究成果報告書)pp.159~166
中村泰輔(2002)「理科教育における物語性指向アプローチとその意味」『教育学研究集録』(筑波大学大学院博士課程教育学研究科) 第26集 pp.107~117
中村泰輔(2001)「過疎地におけるマルチメディアを利用した学校間連携の現状と課題」国立教育政策研究所 公立小中学校における学校間連携の実態に関する調査研究(特別研究「近代教育の変容過程と今後の展望に関する総合的研究」中間報告書第9号)pp.65~76
教育研究業績(その他)
<学会発表>
中村泰輔(2024)「高等学校物理におけるNOSIの理解促進を目指した相互査読活動の実践」日本科学教育学会第48回年会 論文集:pp.711~714
中村泰輔(2024)「NOSIの理解促進を目指した物理分野の指導事例の実証的分析 教職課程学生への試行を通して」日本理科教育学会第72回全国大会 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第23号 p.136
中村泰輔・小林大洋(2023)「NOSI の理解促進を目指した高等学校物理基礎力学分野の授業 オンラインツールを活用した実験計画と発表活動を通して」日本科学教育学会第47回年会 論文集:pp.683~686
中村泰輔(2021)「中学生のもつNature of Scientific Inquiry の理解についての実態調査」日本科学教育学会第45回年会 論文集:pp.575~578
中村泰輔(2021)「中学校理科におけるNOSI の理解促進を図る指導法の実践的検討 中学校理科物理分野「速さ」におけるグループ実験を事例として」日本理科教育学会第71回全国大会 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第19号 p.168
中村泰輔(2020)「高等学校物理分野の課題研究におけるNOSIの理解促進について-物理系課題研究を遂行した高校生への予備調査を通して-」日本理科教育学会第59回関東支部大会(論文集のみで既発表扱い) 発表論文:日本理科教育学会関東支部大会発表論文集 第59号 p.61
中村泰輔(2020)「NOSIの理解を促す中学理科の指導における相互評価の役割 Argument-Driven Inquiry in Physical Scienceの事例分析」日本理科教育学会第70回全国大会(論文集のみで既発表扱い) 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第18号 p.280
小笹哲夫・新谷浩章・小林大洋・中村泰輔・森嶋優理子(2020)「国際バカロレア日本語ディプロマプログラムにおける課題論文(EE)の取り組みについて 化学,生物,物理での実施内容と研究過程の振り返りの考察」日本理科教育学会第70回全国大会(論文集のみで既発表扱い) 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第18号 p.182
中村泰輔(2020)「中学校理科物理分野のオンライン授業におけるNOSIに関する指導の試み」日本科学教育学会第44回年会(論文集のみで既発表扱い) 論文集:pp.443~446
福田成穂・中村泰輔(2016)「高校生が有するNature of Scientific Inquiry の理解の実態:―Lederman によるVASI アンケート調査結果との比較―」日本科学教育学会第40回年会 論文集:pp.265~266
小笹哲夫・新谷浩章・田代淳一・中村泰輔(2015)「英語の教科書で科学を学ぶ : 米国AP(Advanced Placement)プログラムの教科書を利用して」(ポスター発表) 日本理科教育学会第65回全国大会 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第13号 p.550
藤井健司・中村泰輔(2007)「エネルギー環境教育のためのデジタルコンテンツの活用」日本科学教育学会第31回年会 論文集:pp.317~318
藤井健司・中村泰輔・小田島寛・筑波大学エネルギー教育研究会(2006)「高等学校におけるエネルギー教育 : 生徒一人一人に総合的判断思考を促す取り組み」日本科学教育学会第30回年会 論文集:pp.93~94
中村泰輔(2005)「中学校理科における波動の授業 : 物語性の活用を中心に」日本理科教育学会第44回関東支部大会 要旨集:p.70
藤井健司・中村泰輔・小田島寛・吉識典史(2005)「高校学校『理科総合A』におけるエネルギー教育の展開 : その1」日本理科教育学会第44回関東支部大会 要旨集:p.41
藤井健司・中村泰輔・小田島寛・吉識典史(2005)「高校学校『理科総合A』におけるエネルギー教育の展開 : その2」日本理科教育学会第44回関東支部大会 要旨集:p.42
藤井健司・中村泰輔(2005)「高等学校におけるエネルギー教育 : 『理科総合A』の授業を実践して」(これからの日本のエネルギー教育 ~筑波大学エネルギー教育研究会からの発信,課題研究) 日本理科教育学会第55回全国大会 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第3号 pp.63~64
中村泰輔・藤井健司・斎藤利行・板橋夏樹・高橋進吉・伊藤直・桶家久美・畑中敏伸・飯塚貴子・長洲南海男(2004)「アメリカの新しいエネルギー教育の取り組み : "NEED Project"」 日本理科教育学会第54回全国大会 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第2号 pp.359~360
中村泰輔・藤井健司・伊藤直(2004)「高等学校におけるエネルギー教育 : その2「理科総合A」における実践の展開」日本理科教育学会第54回全国大会 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第2号 p.304
藤井健司・中村泰輔(2004)「中学校高等学校における放射線の授業 : その7高等学校「物理II」における実践を考慮して」日本理科教育学会第54回全国大会 発表論文:日本理科教育学会全国大会発表論文集 第2号 p.149
藤井健司・中村泰輔(2004)「中高一貫教育における理科カリキュラムの構築 : その5 実物に触れさせることを意識した総合的カリキュラム」日本科学教育学会第28回年会 論文集:pp.629~630
藤井健司・中村泰輔(2003)「中学校高等学校における放射線の授業 : その6 高等学校「理科総合A」における実践」日本理科教育学会第42回関東支部大会 要旨集:p.18
藤井健司・中村泰輔(2003)「中高一貫教育における理科カリキュラムの構築 : その4 イシューズ指向の新カリキュラム」日本科学教育学会第27回年会 論文集:pp.315~316
中村泰輔・筑波大学エネルギー教育研究会(2003)「アメリカにおける新しいエネルギー教育"NEED Project" : その2 カリキュラムの構成」日本理科教育学会第42回関東支部大会 要旨集:p.20
中村泰輔(2002)「マルチメディアを利用した理科教材における物語性 : "The Great Rescues"を事例として」日本科学教育学会第26回年会 論文集:pp.273~274
藤井健司・畑中敏伸・中村泰輔・中谷幸裕(2002)「中高一貫教育における理科カリキュラムの構築 : その3 新教育課程への対応」日本科学教育学会第26回年会 論文集:pp.359~360
中村泰輔(2002)「アイデアの発生を重視した物理授業の構成 : 光波単元を事例に」日本物理教育学会第19回物理教育研究大会(創立50周年記念大会)発表予稿集:pp.14~15
藤井健司・畑中敏伸・中村泰輔(2001)「中高一貫教育における理科カリキュラムの構築 - その2 中学高校での必修物理」 日本科学教育学会第25回年会 論文集:pp.471~472
中村泰輔・大髙泉(2001)「理科教育におけるストーリー性(1) ――ストーリー性指向アプローチの特質と課題――」日本理科教育学会第40回関東支部大会 要旨集:p.42
藤井健司・畑中敏伸・中村泰輔(2001)「中学校高等学校における放射線の授業 ―その3 放射線の種類について―」日本理科教育学会第40回関東支部大会 要旨集:p.59
飯高隆・川勝均・若嶋江美・三瓶岳昭・中村泰輔・深尾良夫(1999)「北東太平洋地域のCMB直上の地震波速度構造の推定」日本地震学会1999年度秋季大会講演予稿集 発表番号:B34
<講演等>
日本アマチュア無線連盟「東海ハムの祭典」における「届け!若人の声サミット」基調講演(2024.9.29)
南山高等学校(女子部)1年生 探究に関する講演会 講師(2024.11.8)
<実践報告等>
東邦大学理学部教職課程FD講師(2022.2.19) 「高校理科におけるデジタル教科書の活用」
佐藤久・中村泰輔(2019)「Let's enjoy! スクール・ハムライフ 第9回 ARDFへの取り組み」『CQ ham radio』(CQ出版社) 2019年10月号 pp.122~123
後河内聖一・菊一好史・中村泰輔(2019)「Let's enjoy! スクール・ハムライフ 第8回 関西地方の高校無線部の活躍」『CQ ham radio』(CQ出版社) 2019年9月号 pp.132~133
中村泰輔(2019)「Let's enjoy! スクール・ハムライフ 第2回 部活動で行うコンテストの課題と準備」『CQ ham radio』(CQ出版社) 2019年3月号 pp.120~121
中村泰輔(2019)「Let's enjoy! スクール・ハムライフ 第1回 無線部に入る動機、コンテストの魅力」『CQ ham radio』(CQ出版社) 2019年2月号 pp.118~119
中村泰輔(2019)「高等学校におけるアマチュア無線の発展・振興」『CQ ham radio』(CQ出版社) 2019年1月号 pp.98~101
中村泰輔(2018)「全国高等学校アマチュア無線連盟活動レポート」『CQ ham radio』(CQ出版社) 2018年1月号 pp.104~107
小笹哲夫・松崎秀彰・中村泰輔・Yvette Flower・田代淳一(2017)「国際バカロレアDP認定までのプロセス」『サイエンスネット』(数研出版 教授用資料)第58号 pp.14~15
田辺新一・関根康介・中村泰輔、他25名(2017)「スーパーサイエンスハイスクールにおけるルーブリックの活用とその有効性」千葉大学教育学部研究紀要 第66巻第1号 pp.199~203
中村泰輔(2016)「中学生と高校生によるFCCアマチュア無線資格試験へのチャレンジ!」『CQ ham radio』(CQ出版社) 2016年9月号 pp.88~89
中村泰輔(2015)「全国高等学校アマチュア無線コンテスト表彰式・全国生徒交流大会レポート」『CQ ham radio』(CQ出版社) 2015年11月号 pp.142~143
小笹哲夫・新谷浩章・田代淳一・中村泰輔(2015)「APの教科書で科学を学ぶ」『サイエンスネット』(数研出版 教授用資料)第52号 p.10~13
石谷優行・中村泰輔(2014)「全国高等学校アマチュア無線コンテスト表彰式・全国生徒交流大会レポート」『CQ ham radio』(CQ出版社)2014年11月号 pp.84~85
中村泰輔・藤井健司(2006)「電気のエネルギーを体験しよう!」『2006エネルギー教育のすすめ ~教師用指導事例集~ 【中学・高校編】』(発行:経済産業省資源エネルギー庁、製作:財団法人社会経済生産性本部 エネルギー環境教育情報センター)pp.28~33
藤井健司・中村泰輔・小田島寛・吉識典史(2006)「エネルギーについて考える」『2006エネルギー教育のすすめ ~教師用指導事例集~ 【中学・高校編】』(発行:経済産業省資源エネルギー庁、製作:財団法人社会経済生産性本部 エネルギー環境教育情報センター)pp.82~89
特記事項
<表彰等>
第13回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞 指導教諭賞(2015)
文部科学大臣優秀教職員表彰(2016)
<その他>
研究代表者
日本学術振興会 科学研究費補助金 奨励研究(課題番号17906056、2005年度)「物語性を活用した中学校理科教材『波のはなし』の作成と実践」
日本学術振興会 科学研究費補助金 奨励研究(課題番号20H00898、2020年度)「中高生のもつNOSIの実態およびNOSIの理解促進が中学理科・高校物理の探究へ与える影響について」
日本学術振興会 科学研究費補助金 奨励研究(課題番号21H04065、2021年度)「中高物理におけるアーギュメントに着目したNOSIの理解促進を図る指導法の研究」
日本学術振興会 科学研究費補助金 奨励研究(課題番号23H05054、2023年度)「中高理科における模擬学会活動による『科学的探究の本性』(NOSI)の理解促進」
日本学術振興会 科学研究費補助金 研究活動スタート支援(課題番号(課題番号24K22779、2024~2025年度)「小中学校理科における「科学的探究の本性」(NOSI)の理解促進を図る指導法に関する研究」