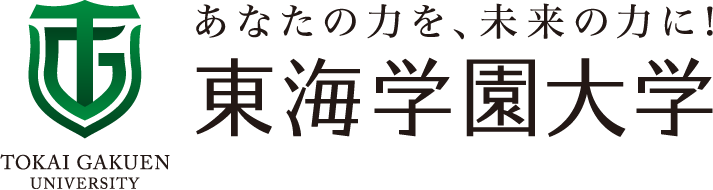学部からの最新情報
心理学部
2022.09.20
平和の書
本年、2022年2月24日(現地時間)、回避の望みも空しくロシアのウクライナ侵攻が始まり、早くも半年以上が経ちました。その間、わたしたちは、人命の尊さは言うまでもなく、世界が、政治・経済・安全保障等々、多くの点で分かちがたく結びついていること(いわゆるグローバル化されていること)に
今日わたしたちは、グローバルという言葉をごくごく当然のように使っていますが、それは、世界が平和で、人的にも物質的にもすべてが比較的うまく回っているという条件付きであることを忘れてはいないでしょうか。言いかえれば、たとえ自国から遠く離れていても、世界のどこかで戦争や紛争が起これば、グローバル化はいとも簡単に崩れる危険をはらんでいるということなのです。卑近な例ですが、わたしたちの日常生活に少し目を向けるだけでも、今回のウクライナ侵攻によって、どれほど食料や資源エネルギーの価格が高騰したかはご存知のとおりです。こうして考えれば、平和であることがいかに重要かつ
* * *
さて、このような状況下で、プーチン大統領が愛読書の一つと挙げたこともあってか、ロシアの文豪で思想家でもあるレフ・トルストイ(1828-1910)の『戦争と平和』が書店での売れ行きを伸ばしているというのです。この作品は、トルストイが足掛け5年をかけ、フランス皇帝ナポレオンのロシア遠征とそれに立ち向かうロシアの人びとの姿を描いた超大作で、登場人物がなんと559人という、19世紀初期のロシアを舞台にした複雑な物語です。が、ロシア文学者の藤沼貴によれば、この作品を通してトルストイが本当に描きたかったのは、「歴史の表舞台で活躍した人々とは違う、普通の人間たちの、日常的で『平和な』生活―生まれ、育ち、愛し、産み、老い、死ぬ、といった平凡だが、しかし、かけがえのない営み―」(1)の大切さであったと言います。
そしてそれは、トルストイ自身、20代で従軍した二度の戦争から身をもって学んだこと―いかなる大義名分があろうと、戦争は残酷で愚かであるという思いから生まれたものでした。晩年のトルストイは、「絶対的平和主義者であり、一切の条件をつけずに、戦争を否定した」(2)と言われますが、彼のこの反戦―あらゆる暴力にたいする
* * *
「インド独立の父」と称されるマハートマ・ガンディー(1869-1948)は、『自叙伝』のなかで、彼を魅了し、また崇敬した人物の一人としてトルストイの名前を挙げ、自らが主宰した『インディアン・オピニオン』紙にトルストイの生き方やその思想について詳しく紹介しています。なかでも、トルストイが、労働と貧困にあえぐ農奴の解放や、農民の子供に対する教育に力を注いだこと、自らも農民と共に肉体労働に勤しみ、労働によって必要な物を手にするのをもっとも、トルストイはあくまで貴族という立場を捨て去ることができなかったという複雑な事情を抱えていたことから、彼の思想と生活の矛盾が非難されたことも事実です。が、それでもガンディーは、非暴力・不服従運動の第一歩を踏み出した南アフリカの地で営んだ共同農園組織に「トルストイ農園」と名付け、厳しい生活ながらも、そこで暮らす人びとと労働を共にし、子供たちに教育を施し、不殺生の生き方によろこびを見出しました。
* * *
トルストイが最晩年(死の2ヶ月前)にしたためた手紙の一つは、ガンディーに宛てたものでした。そのなかで、彼は、ガンディーの非暴力・不服従運動を称賛し、そこでもやはり暴力に対する強い批判を述べ、暴力の使用は、生の最高の法である愛とは両立しない、と記しています。さて、19世紀から20世紀にかけ生きたトルストイやガンディーの思想や行動は、もはや、過去のもの、時代遅れのものなのでしょうか。21世紀に生きるわたしたちは、社会や文明の進歩の下に、
『戦争と平和』では、ロシアがナポレオンによって侵攻され、多くのロシア人が犠牲になりました。そして今、ロシアがウクライナに侵攻しています。もし、時代と共に人間が本当に賢明になるのであれば、わたしたちは、戦争を幾度も繰り返すでしょうか。
「暴力は、生の最高の法である愛とは両立しない」、「平凡だが、かけがえのない日常の営みこそが平和」であると信じ行動したトルストイやガンディーの思いを、わたしたちは、今一度、しっかりと受けとめるときなのかもしれません。分断ではなくグローバルな世界には、何にもまして、平和が最も重要なのですから。
森本素世子(インド英語文学)
(1)藤沼貴『トルストイの生涯』レグルス文庫 第三文明社 1993年 p.123
(2)前掲書 p.209