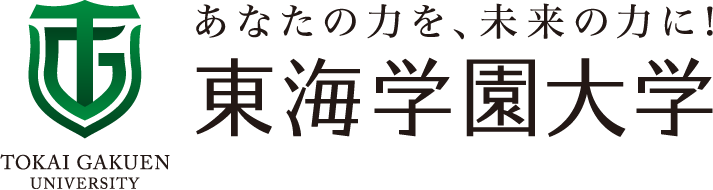「スン」と「はて?」に関する一考察
今期のNHKの朝ドラ「虎に翼」が好評である。日本初の女性の弁護士であり、のちに日本で初めて女性として裁判所所長を務めた三淵嘉子さんをモデルにしたドラマである。戦争や男女差別など、かなり重いテーマを扱っているが、主役の猪爪寅子を伊藤沙莉さんが大変魅力的に演じている。そこでシビアな事態をユーモラスに描くことに一役買っていると思われる、「スン」と「はて?」を取り上げてみたい。
「スン」の登場する一幕を紹介しよう。寅子の兄直道と寅子の親友花江の結婚の準備について、両者の父親たちが労われる場面である。実際に準備に奔走した直道の母親と花江の母親は、男たちの様子を見て「スン」とした表情で黙っているのである。この「スン」に辞書的な解説を加えるなら、
①心に不満や葛藤を抱えながら、表情を変えず黙っているさま
②他者と理解し合うことを諦めて、コミュニケーションを放棄するさま
となるだろうか。
一方、「はて?」は寅子が納得できなかったり、何か引っかかりを感じたりしたときに発するセリフで、たとえば、このような場面があった。戦後に、父、兄、夫を亡くして一家の大黒柱となるべく司法省で働き始めた寅子に対して、明律大学時代の恩師の穂高が、自分が法の世界に導いたことで佐田君を不幸にしてしまったと謝罪した時である。「えっ?不幸?私が?はて?」。そして、「戦争や挫折でいろいろ変わってしまったけど、好きでここにいます。」と、改めて法律の世界で生きていくことを決意するのである。こちらを辞書的に解説するなら、
①あたりまえとされていることを疑い、異を唱えようとすること
②心に生じた違和感に向き合い、それを他者に発信すること
になるだろうか。
寅子が女学校や明律大学で学んでいた頃の戦前の日本は、法律上の女性の地位は低く、人々の意識も男女平等とは程遠く、女性が意見を言ったり、自分の意志を通したりすることが難しい時代であった。女性が「スン」で切り抜けざるを得ない場面も多かっただろうこの時代に、「はて?」を発動することは勇気のいることだっただろうと想像する。
戦後日本は、日本国憲法によってすべての人の平等が謳われることになったが、令和6年の現状はどうだろうか。
先日、世界経済フォーラム(WEF)がまとめた2024年版「ジェンダーギャップ・レポート」1)が発表された。ジェンダーギャップ・レポートは、各国の男女格差を「経済」「教育」「健康」「政治」の4分野で評価し、国ごとのジェンダー平等の達成度を指数にしている。「0」が完全不平等、「1」が完全平等を示し、数値が大きいほどジェンダーギャップが小さいことを表している。「ジェンダーギャップ指数ランキング」で、日本は146か国中118位であった。
国会議員や閣僚の男女比などから算出される「政治」の指数は0.118で113位、男女の賃金格差や管理的職業従事者の男女比などから算出される「経済」の指数は0.558で120位、出生時の性比や健康寿命の男女比から算出される「健康」の指数は0.973で58位、識字率、中等教育就学率、高等教育就学率の男女比から算出される「教育」の指数は、0.993で72位であった。
「政治」「経済」に関する指数(達成度)の低さやランキングの低さについては、この結果が公表されてから、さまざまなメディアが取り上げていたが、「健康」「教育」については、男女平等がほぼ達成されているとみなされているのか、批判的に取り上げているメディアはほとんど見当たらなかった。内閣府男女共同参画局も、『「教育」と「健康」の値は世界トップクラス』と表現している2)。しかし、私は、この「教育」の結果に衝撃を受けている。
「教育」の結果を詳しく見てみよう。識字率、中等教育就学率の指数(ジェンダー平等達成度)は1.00で当然1位であるが、高等教育就学率の達成度は0.969で107位である。ほぼ問題がないかのように扱われる教育の分野の男女格差であるが、日本の高等教育就学率の指数(ジェンダー平等達成度)は146か国中107位なのである。
大学進学率の男女差はほんの少ししかない。いや、そうではない。大学進学率の男女差は確かに存在するのである。この認識の違いは大きい。指数の0.969は低くないようにも思えるが107位なのである。他国との比較からは、日本の性別役割意識がはっきりとみえる。これは小さな問題にみえて実はとても大きな問題なのではないだろうか。
高卒であるか大卒であるかによって、賃金は変わる。また、高卒であるより大卒である方が管理職につく可能性が高いかもしれない。また、大学での学びが政治参加に繋がる可能性もある。言い方を換えると、日本では、女性は社会に出て働かないから(働いても結婚したら辞めるから、出産したら辞めるから)、管理職にはつかないから、政治にも参加しないから、大学に進学しない(させない)でいいと考える人たちがいるのかもしれない。昔も今も。大学進学に関する意識の男女差(進学する本人の意識だけでなく、進学をサポートする親世代の意識)が、「政治」や「経済」での男女格差が大きい日本の社会を作っているのではないだろうか。このレポートは、身近な意識が社会を作るということを、実感をもって理解させてくれる。
また、東京大学や京都大学の学部学生の男女比は約8対2であり、世界の一流大学のなかでも極めて偏っており、その他の有名国立大学でも女性比率が40%に達していない。これも大学進学に関する意識の男女差の影響のひとつだろう。東京大学の教授である矢口は自身の著書『なぜ東大は男だらけなのか』の中で、このような日本の大学の現状は、「日本社会全体のジェンダー構造と不可分な関係にある」と指摘する(矢口,2024)3)。「有名大学の卒業生が大手企業や官公庁に就職し、社会のリーダーとなっていくというのがいまだにキャリアの定番とされるこの社会において、それらの大学に女性の姿が圧倒的に少ないのであれば、女性が社会の第一線で活躍できる可能性はおのずと限られてしまう」。
このように、日本はまだまだ男女格差が大きいと言わざるを得ない。しかし、憲法で平等が定められて80年近くが過ぎてもなお続いているこの格差を、私たちはしっかりと自覚できているだろうか。私たちは改めて、「はて?」の意識を強く持つ必要があるのではないだろうか。
「虎に翼」に話をもどそう。女学生時代、明律大学の女子部時代には、「はて?」を連発していた寅子であるが、妊娠し弁護士を続けることが難しくなり、弁護士事務所を辞めてからは、発せられなくなった。そして久々に発動したのが、先に紹介した穂高とのやりとりではなかったかと私は記憶している。弁護士を辞めたことは寅子にとって大きな挫折であり、このことに対して寅子は大きな罪悪感をもっており、しばらくは「はて?」を発動させられなかったようにもみえる。「はて?」は自分に生じた違和感や、それを生じさせたものとの対決であり、一度降参して弁護士を辞めた寅子は、対決を放棄してしまった、あるいは、自分には対決する資格がないと諦めてしまったようにも思える。久しぶりの「はて?」が発動されたとき、そばにいた桂場がやっと出た!という表情で笑うシーンを私は忘れられない。
久しぶりの「はて?」のきっかけになった穂高の謝罪であるが、これが心から寅子を思っての言葉であることもとても興味深い。穂高は寅子に期待をかけ、弁護士になるべく応援しそれを見守ってきた人物である。弁護士として働いている寅子が妊娠していることを知り、仕事をしている場合ではないと、寅子の勤める事務所に連絡し、所長の雲野の、今は子育てに専念する時だという助言に同意する。弁護士を辞めた寅子に対して、自分のせいで余計な経験をさせて不幸にした、と考えているのである。穂高に悪意はない。仕事をしている場合ではないという助言は、寅子の身体を気遣っての言葉であり、女性が子どもを産み、育てながら仕事をするという選択をするなど考えつかなかったことによるものだろう。しかし、そもそも寅子は弁護士としての仕事をするために結婚を決意したのだった。女性がひとりで信用を得ることが難しい時代であり、寅子は仕事を依頼してもらうため、社会的地位を得るための結婚をし、その結果、子どもを授かったのである。この時代の女性は、結婚していないと一人前とみなされず仕事をすることも難しかったこと、そして、寅子がどれだけの使命感と責任感で弁護士の仕事を続けてきたのかを穂高は知らなかった。同じ法律の世界にいても、穂高と寅子は体験している世界が違っていたのだろうと推測する。
「はて?」と発しなければ、何か違うとこちらが感じていることは相手には伝わらない。体験の違いがあるのだから、考え方も感じ方も違うということを大前提に、私たちはもっと「はて?」を連発しないといけないのではないだろうか。面倒がられることを恐れずに。
ここで再び「スン」にも触れておく。寅子の母はるは、「頭のいい女が確実に幸せになるためには、頭の悪い女のふりをするしかないの」と言いながら、「この新しい昭和の時代に自分の娘には「スン」としてほしくない」と、寅子に六法全書を買い与え、明律大学で学ぶことを認めた。これからの時代を生きていく寅子に対する、自分が感じた違和感を無視せずきちんと向き合いなさい、周りと理解し合うことを諦めず、コミュニケーションをとりなさいという、はるからのメッセージのように感じられる。「スン」は女性だけのものではない。花岡たち明律大学の学生が、梅子の息子たち帝国大学の学生と甘味処で鉢合わせたとき、明律大学の学生は「スン」となった。自分と違う道を、軽々と歩んでいるように見える人を目の前にしたとき、人はコミュニケーションを諦めて「スン」となるのかもしれない。
「スン」をやめ、「はて?」を発動していくことは、男女の違いだけでなく、さまざまな違いをもつ人たちがお互いを理解するための第一歩になるのではないだろうか。
1 ) Global Gender Gap 2024- Insight Report, June 2024,World Economic Forum p.219
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf 2024年7月2日閲覧.
2 ) 内閣府男女共同参画局(2024).「男女共同参画に関する国際的な指数」,『内閣府男女共同参画局ホームページ』.
https://www.gender.go.jp/international/int_syogaikoku/int_shihyo/index.html 2024年7月2日閲覧.
3 ) 矢口 祐人(2024).なぜ東大は男だらけなのか 集英社