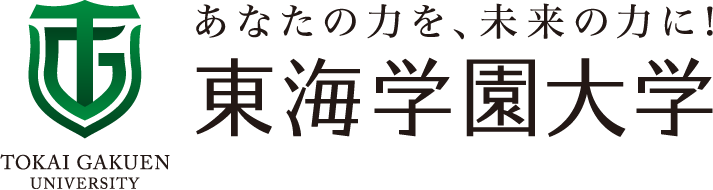デザインと心理学

写真. デザイン心理学の授業風景の例(テーマはユニバーサルデザイン)
本学心理学部には「デザイン心理学」という授業があり、「デザイン心理学研究室」が設置されています。
デザインと心理学と何が関係あるの?と思う人もいるかもしれませんね。
しかし、デザインも心理学も、その中心にあるのは人間です。
ですから、本学心理学部にはデザイン心理学もその他の様々な心理学のうちの一つの領域として仲間入りしています。
そこで今回は、デザインの基本的な考え方とデザイン心理学についてお届けします。
デザイン≠表面的な見た目
デザインという言葉は日常でもしばしば使われますが、皆さんはどんなイメージを持っていますか?
もし、デザインを表面的な見た目のこと「だけ」だとイメージしているなら、ぜひ知って欲しいことがあります。
デザインは、「物の材料や構造や機能はもとより、美しさや調和を考えて、一つの物の形態あるいは形式へとまとめあげる総合的な計画、設計」のことをいいます(勝井ら, 2012)。
ラテン語では「意図や輪郭を明確に示す」「考案する」を意味する「désignáre」に由来し、現在では世界中で「デザイン=design」が用いられています。
つまり、デザインは表面的な見た目のみを指すのではなく、「意匠」、「設計」、「計画」、「構造的仕組み」という意味を含んでいます。
実際に、本学心理学部のいくつかの授業でもデザインという言葉が使われます。
例えば、「レポートのデザイン」や「実験デザイン」という言葉。
「レポートのデザイン」は、レポートの「意匠」を意味するときもありますが、「構造(的仕組み)」という意味で使われることもあります。
「実験デザイン」は、実験の「設計」「計画」という意味であり、明らかに実験の表面的な見た目という意味ではありません。
ちなみに、本学心理学部では、レポート作成は1年次から、実験は2年次から全員が取り組むことができます。
デザイン心理学について
「デザイン心理学」は、デザインの問題を心理学的なアプローチで解決することを目指す学問領域です。
授業は、デザイン心理学の理論と実践(制作・調査・発表・評価)を通じて、心理学的視点から「よいデザインとは何か」を考察するとともに表現する力を涵養することが目的です(写真1)。
通常、1年次の春学期に開講され、入門的な心理学的テーマを紹介した上で制作をします。
中にはデザインセンスに自信がない、画力がない、と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫。
この授業では見た目の良し悪しでは評価しません。
また、デザインも学問ですから、学んで、練習すれば、誰でもデザインのスキルを向上させることができると考えています。
デザインと心理学。
授業を通じて観察眼を身につけることで、普段の生活においてもデザインと心理学が密接に関連していることに一層気づくようになるでしょう。
引用文献
勝井三雄・田中一光・向井周太郎 監修(2012). 現在デザイン辞典2012年版 平凡社