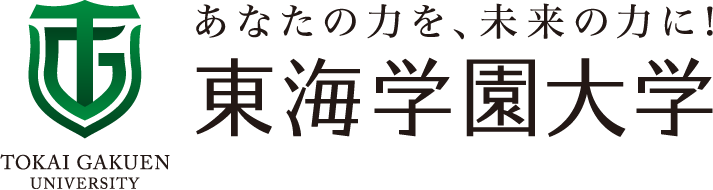フラッシュバックと「私」
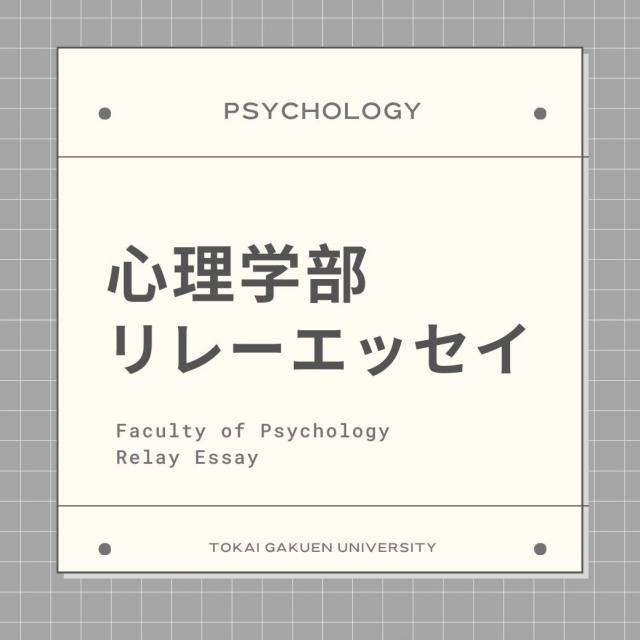
フラッシュバックと呼ばれる技法が映画や小説にある。「現在」の中に「過去」が出現してそこから話をたどるわけであるが、たとえば同じV・ナボコフの『ロリータ』(「ロリコン」という表現はこれに由来する)が原作だが、フラッシュバックを用いたS・キューブリック監督『ロリータ』のほうが、用いないA・ライン監督の『ロリータ』よりもおもしろい。他方、原作が同じE・ヘミングウェイで、「ファム・ファタール」(運命の女)に翻弄された挙句、映画の冒頭で殺される男のフラッシュバックは用いない、D・シーゲル監督のリメイク『殺人者たち』のほうが、フラッシュバックが用いられ、時系列に従って話が展開し件の男が映画の結末で殺される前作のR・シオドマーク監督『殺人者』よりもおもしろいので、フラッシュバックを使えばよいというものではない。ちなみにD・シーゲル監督のSFスリラー『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』ではフラッシュバックが用いられ主人公が物語を展開し、観客の「現在」へと至って臨場感を高めている。
ところで、「ロリコン物」であり、かつまた「ファム・ファタール」が常連の「フィルム・ノワール」(いわゆる犯罪映画)の分野で有名なO・プレミンジャー監督の『ローラ殺人事件』では興味深い現象がみられる。物語の最後で殺される人物が冒頭のフラッシュバックの部分で「私は・・・」と「自己告白」を始めるのだ。つまり亡くなった存在しないはずの人物が「語っている」のだ。この「矛盾」を解決する試みの一つが、B・ワイルダー監督の『サンセット大通り』である。自らサイレント時代以来(?)の大物女優を演ずるグロリア・スワンソン主演の映画だが、その終わり近くで、映画の「現在」においては執事役を演ずる、これまた自らサイレント時代以来の名監督=怪優E・フォン・シュトロハイムが撮影キャメラを回しているシーンが映し出されるのだ。つまり映画の最後で射殺される若き脚本家役のウィリアム・ホールデンが冒頭からナレーションを務める『サンセット大通り』という映画自体の撮影を行っているという設定なのだ。したがって射殺されたホールデンは映画が終了しても「生きている」のだ。もちろん映画の「筋」としては、殺人事件を報道するために駆けつけた記者たちを執事が監督として指揮、撮影したということになるが、これはいわゆる「自己言及」、「映画についての映画」とも言える。そして先の「矛盾」を解決した観客は、この作品の監督が「本当は」ワイルダーであることを思い出して「安心」する。
しかし、その時、観客はこの「映画」から「遠く離れて」いる。この表現は、J=L・ゴダール、A・レネなどのオムニバス監督作品『ベトナムから遠く離れて』のタイトルから引用したもので、とりあえず「現場」から離れていることの「自覚」を示すが、F・フェリーニの『8 1/2』、F・トリュフォーの『アメリカの夜』などを初めとする「メタ映画」がもはやインパクトを失っていることをうかがわせもする。ちなみに監督6人の合作である『ベトナムから遠く離れて』では、処女長編『勝手にしやがれ』以来、「メタ映画」ばかり撮ってきたゴダールただ一人が画面向かって左向きになってキャメラとそのファンダ―を覗く位置にいるという構図(これは『サンセット大通り』でフォン・シュトロハイムが「撮影開始!」と号令をかける場面の構図と同じである。なお、『ベトナムから遠く離れて』から18年後の作品『ゴダールの探偵』にはシュトロハイムのシーン自体の引用がある)だけでなく、キャメラとともに観客を正視する画面(キャメラが「観客」を「直視する」というあざとい構図だ)も映し出していて、「遠く離れて」あること、映画の「自己批評性」を示している。『勝手にしやがれ』やA・ヒッチコックの遺作『ファミリー・プロット』の末尾でヒロインたちが観客に送る「ウインク」(目配せ)が観客に「自己批評」(「私」は今まさにこの「映画」を見ているという自覚)を呼びかけるのと相まって、いまや映画が「メタ映画」であることは当たり前であるが、それは同時に映画がインパクトを失う危険性を伴うことなのかもしれない。