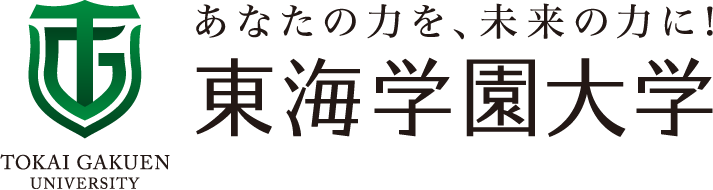「三人よれば文殊の知恵」は本当なのか?
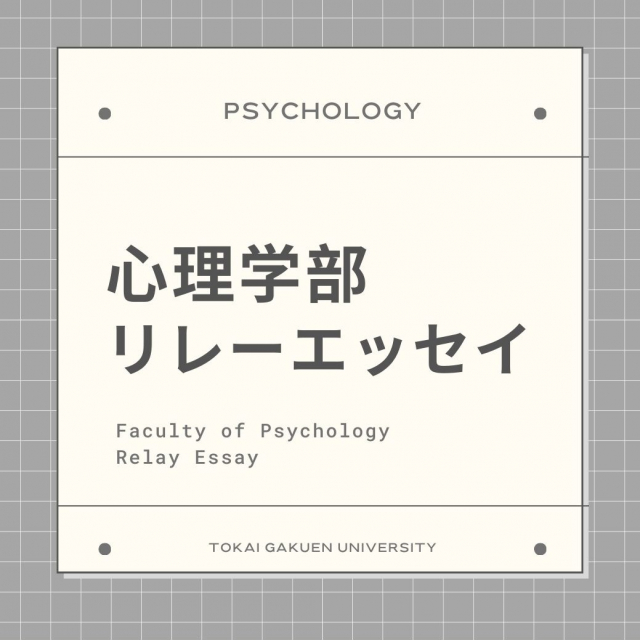
一般的に「三人よれば文殊の知恵」ということわざに表れているように、複数人で話し合うことは一人で考えるよりも優れた結論に導くと期待されています。しかし、実際には集団で話し合うことによって、必ずしも望ましい結果が得られるとは限りません。いくつかの心理学的研究では、集団が意思決定を行う際に生じる問題点が明らかにされています。
その一つに「リスキーシフト」という現象があります(Stoner,1961)。これは、集団で下された意思決定が個人の決定よりもリスクを伴う傾向があることを指しています。例えば、スペースシャトルチャレンジャー号の打ち上げ失敗のような歴史的事例においても、リスキーシフトの影響が見られます。
また、リスキーシフトという現象だけではなく、安全な方向へ結論が傾くことも知られています。そこで「集団分極化現象」というより包括的な概念が導入されました。これは、集団内の議論を通じてメンバーの意見が平均化されるのではなく、むしろより極端な方向に傾くという現象を示すものです。MoscorviciとZavalloni(1969)の研究によって提唱されたこの概念は、集団がリスク志向に偏ることもあれば、逆に安全志向に傾くこともあることを示しています。
このような分極化現象が生じる原因としては、まず同調行動が挙げられます。議論の中で多数派の意見が優位となり、それに同調する形で議論が進むため、意見が特定の方向へ偏るのです。Kameda(1991)の模擬裁判員実験では、多数派の意見が合議や判決に強い影響を及ぼすことが示されました。また、集団のサイズが大きくなると、分極化の傾向がさらに強まることも明らかにされています。
さらに、集団での意思決定においては「集団浅慮」という問題も生じることがあります(Janis,1972)。個人では適切な判断ができるのに、集団での協議によって誤った決定に至ってしまうことを指します。Janisはアメリカ政府の歴史的失敗、たとえば真珠湾攻撃、ベトナム戦争、ウォーターゲート事件を分析し、集団浅慮の特徴を明らかにしました。この現象は、メンバー間の結束力が高く、異なる意見を出しにくい閉鎖的な集団において特に生じやすいとされています。特徴としては、「自分たちは間違わない」という無根拠な過信、外部からの忠告の軽視、都合の悪い情報や反対意見の遮断などが挙げられます。これらを放置すると、他の選択肢を十分に検討せず、リスクやコストを軽視し、緊急事態に備えないといった意思決定上の欠陥が生じるおそれがあります。
このように、集団での意思決定には多くの利点がある一方で、特有の落とし穴も存在します。それらのリスクを理解し、構造的および心理的な対策を講じることによって、集団討議はより建設的で実りあるものになると考えられます。