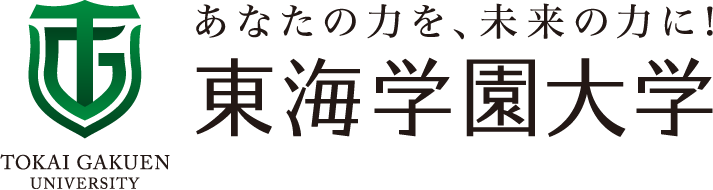人文学部心理学科リレーエッセイ(「不思議?を抱いて」)
毎夜、夕食の用意に台所に立って、視線を上げると、磨りガラスの窓の向こうにヤモリが一匹、餌を狙ってか、白いお腹を見せてじっと身動きもせずに張り付いています。ヤモリなど気持ちが悪いという人も多いでしょうし、確かに私自身も触るのは少しはばかられます。が、元々日本では、「守宮・家守・屋守」といった漢字が当てられていることからもわかるように、ヤモリは「家を守ってくれる」縁起のよい動物、そして台所の灯りに寄ってくる害虫を食べてくれる有り難い生き物なのです。
さて、このヤモリを見るたびに、「それにしても」といつも思うことがあります。
それは、人間の進化の過程です。おそらく皆さんも、今までに、中学校の理科の時間に動物の発生・進化について学んでこられたと思いますが、発生初期の胚の時点では、魚もヤモリも私たち人間も、ほとんど皆、同じ姿をしています。もちろんこうした私の「不思議?」は、すでに学問的には解き明かされてはいるのです。それでもなお、人間が、母親のお腹の中では、魚のように水(羊水)のなかにいて、生まれるとしばらくは、ヤモリのようにお腹を擦りながら両手・両足をパタパタ動かして前に進み(なかには後ろに進む赤ちゃんもいますね)、そして、やがては、四つ足で歩く哺乳類のように、もう少ししっかりと四つん這いでハイハイするようになり、それから、チンパンジーのように危なっかしく立ち上がり、やっと二足歩行になる、という、何億年もかけて成された壮大な進化の過程を、たった数年の間に経験しているという事実は、私にとっては、やはり「不思議」であり、思っただけで、ワクワクするのです。
生命をミクロの世界まで探究できるようになった現代科学においては、私の「不思議?」など、原始的なものと一笑されてしまうかもしれません。それでも、こうした進化を秘めた人間が、星々のまたたく大いなる宇宙(マクロ世界)にあって、この地球にだけ(?)存在し(少なくとも今はまだ、地球人の知る限り、私たちのような生命体は他には発見されておりません)、長くて100年余の命を終えていくというのは、驚嘆すべきことではありませんか? そして加えるなら、大いなる宇宙の端っこは?
こうして、「起き上がりこぼし」のように、「不思議?」が頭の中でたえず上下左右に動いていると、大きな世界だけでなく、身近な世界もますます興味のあるものに思えてきます。そして、そこに立ち止まって、少し考えてみることで、私たちの人生はより豊かなものになるといえましょう。
アジアで初めてノーベル文学賞を受賞した、インドの詩人ラビンドラナート・タゴールの詩に、神であるあなたが、種から芽を出させ、蕾を花に、花を果実に育て実らせてくれる、という素敵な言葉があります。小さな種のなかに、目には見えないけれど、さまざまに咲き・実る、心躍る可能性が内在している、と。この美しい「不思議」に導かれ、私たちも個々に花開き、実っていくのです。
「それにしても」と、また思うのです――ヤモリが食べてくれる虫たちのことを、いったい誰が害虫と決めたのでしょうか?
森本素世子(インドの英語文学)