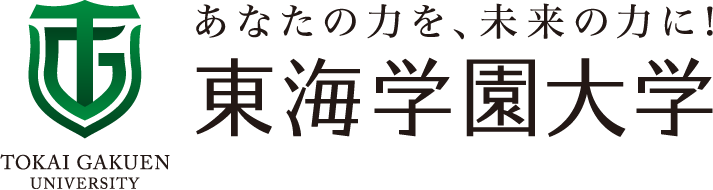「味覚について」
人間のいわゆる「五感」のなかで、視覚、「見る」が「理解する」や「分かる」といった高度の認識能力の比喩に使われることは珍しくない。これに対して「触れる」という感覚は、より原初的な次元のものとして言及されることが多い。そして両者の対比のポイントとして、「視覚」においては「見る者」と「見られるもの」とが明確に区別され、「見る者」が一方的に何かを「見る」という両者の隔たりが強調され、「触覚」においては、手と手を合わせた場合のような「触れるもの」と「触れられるもの」との交換可能性、あるいは両義性が強調される。
ところで、五感のなかで「味覚」に注目してみると、その中核的な働きは「触覚」であるかとも思われるが、実際には、御馳走の「見た目」、「香り」、「舌触り」さらにはBGMの響き(食事中の「会話」はどうだろうか)を勘案すれば、「味覚」の働きは「五感」の働きを総合したものとも思われる。ちなみに博物学者のリンネにより命名された「人間」の学名’homo sapiens’は直訳すれば「賢い人」ということであり、’sapiens’は動詞’sapio’(味わう)に由来する。そう、「人間とはよく味わうことができる存在」なのだ。
かつて中村雄二郎はその著書『共通感覚論』(岩波書店)において、アリストテレス伝来の、「五感」に共通する感覚である「共通感覚」の歴史的な意義を強調した(たとえば英語に翻訳すると’common sense’、すなわち「常識」となる)。他方’sapio’から派生した’sapientia’は、’scientia’(いうまでもなく’science’の元になった語)の上位に位置づけられる概念を表す語で、「知恵」と訳されたりもする。単なる「知識」の丸暗記ではなく、人格と深く結びついた「知恵」ということである。ここではしなくも、五感のなかでも特に「味覚」の働きが五感を統合する「共通感覚」のそれと重なってくる。
某TV番組でもおなじみの、フランスの美食家ブリア-サヴァランの有名な言葉、「どんなものを食べているか言ってみたまえ。君がどんな人間か言いあててみせよう」(ブリア-サヴァラン『美味礼讃』岩波文庫)が単なる警句ではなく、ヨーロッパの精神史に裏付けられた滋味豊かな言葉に思われてくる。
片桐茂博(哲学)