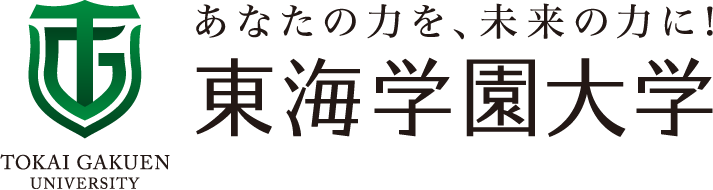文化による人の心への影響
人の心は生まれつき決まっているのでしょうか。それとも生まれてから周囲の環境の影響を受けて決まるのでしょうか。これは「氏か育ちか(nature or nurture)」論争と呼ばれており,心理学だけでなく哲学や科学において長い間問題となってきました。これを別の言葉で言い換えるならば,人の心は遺伝的に決定されているのか,環境の影響で形成されているのかと言うことができるかもしれません。現代の心理学では,人の心の形成に影響を与えているのは,遺伝と環境の両方であり,心はその相互作用で決まっていくと考えられています。
人の心にとって,環境として重要な役割を果たしているのが「文化」です。もともと心理学は人の心が共通して持っているメカニズムについて検討することを主な役割としてきたので,長い間,心に対する文化の影響についてあまり検討してきませんでした。しかし,1990年代になったあたりから文化心理学と呼ばれる研究領域が盛んになって,文化の影響が本格的に検討されるようになってきました。
社会心理学の領域で取り上げられているテーマとして自己高揚傾向があります。簡単に言えば,人は自分のことを良いと思いたい,他人よりもすぐれていると思うなどの傾向を持っているということです。この傾向はアメリカで発見され,調査や実験で何度も確かめられてきました。心理学という学問の中心はアメリカですので,アメリカで確かめられた自己高揚傾向についても,人間が持っている共通した傾向と考えられ,その知識は世界に広まっていきました。
しかし,この自己高揚傾向が,実はアジア圏では必ずしも生じないことが明らかになりました。ご存知の通り,アジアにある日本では自己卑下や謙遜の文化があるために自己高揚傾向があまりみられないのです。この自己高揚傾向の文化による違いにマーカス先生と北山先生は着目して,人の心は自分たちが考えている以上に文化に影響を受けていることを指摘しました。これは現在の文化心理学という領域の始まりの1つと考えられます。
自分たちの文化は,まるで空気のように自分の周囲に存在するために,なかなか自覚することができません。しかし,異なる文化と比較することによって自らの文化の特徴に気づくことができます。例えば,海外旅行などをしたり,海外からの留学生や教師と接することによって,自らの文化が他の文化とは異なることに気づくことができるのです。
現代はグローバル社会と呼ばれ,多様な文化を尊重することが望まれています。その時,人の心が各々の文化によって,どう影響を受けているのかを知ることは大切になってくるでしょう。文化心理学を学ぶことによって,そのような視点を獲得することが可能になると思います。
伊藤君男(社会心理学・認知心理学・実験心理学)