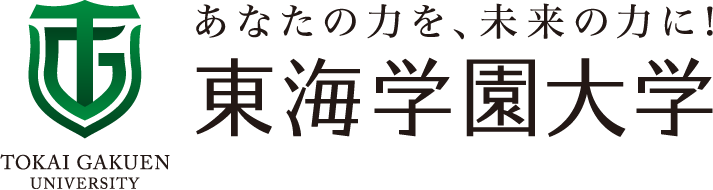文字について
文字を記すのが大流行りだ。ソーシャル・ネットワーキング・サービスが広く普及して、みな、こぞって文字を電子機器に入力している。SNSのやりとりにはもちろん動画や写真も使えるが、それにしてもほぼ必ず文字を添えることになるし、込み入ったことを伝えるにはたいてい文章が必須だ。SNSに熱中している人々はつねに文字を書いていることになる。そう、最近は小学生だって文字で噂話をするのだ。さらに今や、事務系の仕事の多くも電子メールのやりとりなしには考えられなくなった。インターネットが普及する前に比べ、(内容はともかく)人々が書き記す文字量は極端に増えている。
文字は驚くべき技術である。われわれは「心」の中に言語的な情報をもっているが、これは時間とともに流れていって、記憶できないものは消え去ってしまう。そこで、心の内容や重要な事柄をいつでもよみがえらせるため、言語を記号に置き換えて物体の上の何らかの痕跡として記録することが考案された。記号は、自分だけのものだと誰にも伝わらず不便なので、多くの人に書き方と意味を伝えて共有した。平易な文章に限ってもわれわれが使っている単語はかなりの数になるから、それを表現するだけの記号の体系が必要になる。
ひとたび体系が完成して広く共有されれば、文字は時空を超えて「心」を伝える。大昔の人々が作った詩歌にのって生き生きと感動が伝わる。場所も時代も隔たり、直接会うことがかなわない人々の、思考、感情、イメージもある程度再現できる。文字こそが、精神の封入された容器なのだ。
人類史を眺めれば、文字はおそらく税務などの数字を記録する必要から生じ、楔形文字、ヒエログリフ、亀甲文字など、数千年前には一部の地域で一部の人々が使えるようになり、その後さらに各地に飛び火して発展していった。そして過去の出来事、社会的ルールの正確な記述をはじめ、思想や技術や感情さえもが直接人を介さずに拡散し、いつでも参照できるようになった。これは、貨幣などと並んで、近代社会成立に欠かせない決定的なインフラのひとつである。
と、ここまではよい。農耕が開始され、ある程度社会が分業化して事務的な仕事や祭司などを専門にする人々が増えれば必ず文字が発明されただろう。むしろ、いっそう驚異的なのは、訓練によってほとんどの人がそれをすばやく巧みに使いこなせるようになることだ。
話ことばと根本的に違って、書字は長期間にわたる意図的な努力をしなかったら絶対に習得できない面倒な技能だ。未だに文字をもたない民族だっている。世界全体の識字率が50%を超えたのは1950年代頃と推定されるし、いわゆる先進国でもほとんどの人々が文字を使えるようになったのはここ百年前後のことだ。
とはいえ、幸運なことにわれわれの社会は、教育を普及させることによって大規模な文字の共有に成功した。そして、文字に習熟した後は、たとえば考えたことを紙にさっとメモするのは容易である。さらに訓練をすれば、キーボードやフリック操作による文字入力も素早くできるようになる。われわれは複雑な楽曲を弾くピアニストの指先に驚嘆するが、よく考えてみればかなり近いことをみんなやっている(義務教育の間だけでも10年近く文字を書く練習をするわけなのだが)。
では、書字と読字はどのようにして可能になるのだろうか。これまで、心理学的な(認知的な)モデルと、それに対応する脳領域が研究されて来た。字が書けるのは人間だけだから動物実験によって書字能力を調べることができない。したがって、わかっていないことも多いが、確実なのは、頭の中の複数の情報処理システムが関わっていることだ。文字の形を見て何の文字かを理解するには視覚的な処理が必要だし、音をもった言葉として理解するには音韻的な処理が関わる。これらの処理には、左脳の、もともと空間認知を担当していた部分の一部が流用されているらしい。別々のものとして備わっていたいくつかの機能を組み合わせて高速で働かせるため、一部の空間認知能力が犠牲になっているわけだ。さらに長期記憶に蓄えられた意味情報を引き出してこなければ内容が理解できない。そしてすばやく文字を書くには指先の繊細な運動制御が加わる。その上で、読み書きという高級技能は実現されている。脳の機能局在をも変化させ、認知システムの神業のような協調を得て、精神は時空を越える容器を獲得したのである。
河野和明(感情心理学)
参考文献
相場恵美子 (2002). 失読・失書の認知モデル 新潟医療福祉学会誌, 2, 111-118.
ハラリ, Y.N. 柴田裕之(訳) (2016).「サピエンス全史-文明の構造と人類の幸福」上下 河出書房新社
インフォビジュアル研究所 (2017). 「図解でわかる ホモ・サピエンスの秘密」 太田出版
櫻井靖久 (2011). 非失語性失読および失書の局在診断 臨床神経学, 51, 567-575.
鈴木光太郎 (2013).「ヒトの心はどう進化したのか」 筑摩書房
ロスリング, H., ロスリング, O., ロスリング, A. R. 上杉周作・関美和(訳) (2019). 「FACTFULNESS(ファクトフルネス)」 日経BP
van Zanden, J.L., et al. (eds.) (2014), How Was Life?: Global Well-being since 1820, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264214262-en