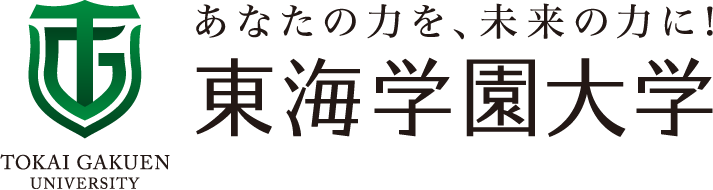人は合理的な判断ができているか?―確実性効果
早速ですが、以下の(A)と(B)の二つの選択肢のうち、好きな方を一つ選んで下さい。
(A)100%の確率で30,000円をもらえる。
(B)80%の確率で40,000円をもらえ、20%の確率で何ももらえない。
おそらく、多くの人が(A)を選んだのではないでしょうか?しかしながら、「期待値(=ある試行を行った時、それぞれの値が生じる確率を考慮し、結果として得られる値の平均値)」を計算すると、より多くの金額をもらえる可能性が高い選択肢は(B)であると言えます。
具体例を用いて説明します。まず、(A)を10回選択した場合、もらえるのは300,000円です(30,000円×10)。それに対し、(B)を10回選択して確率通りの結果(80%)であった場合、もらえるのは320,000円となり(40,000円×8)、(A)よりも大きい金額になっています。それにも関わらず、多くの人が(A)を選んだということはどういうことなのでしょうか?
このような「不確実な利得よりも確実な利得を高く好む傾向」は「確実性効果(certainty effect)」と呼ばれています。何も得られない確率が非常に小さい場合や期待値的に不利である場合であったとしても、人は何も得られない可能性がある選択肢よりも確実な選択肢を選びやすい傾向があるのです。
「受験でどの学校を受験するか」、「どのような保険に加入するか」、「新生活で住む場所をどこにするか」など、世の中には何らかの選択をしなければいけない場面が多くあります。「確実性効果」のように、時として人は誤った判断をしてしまうことを考慮した方が、より望ましい結果に繋がると考えられます。
参考文献: 竹村 和久 (2015). 心理学の基礎 専門編11 経済心理学―行動経済学の心理的基礎 培風館